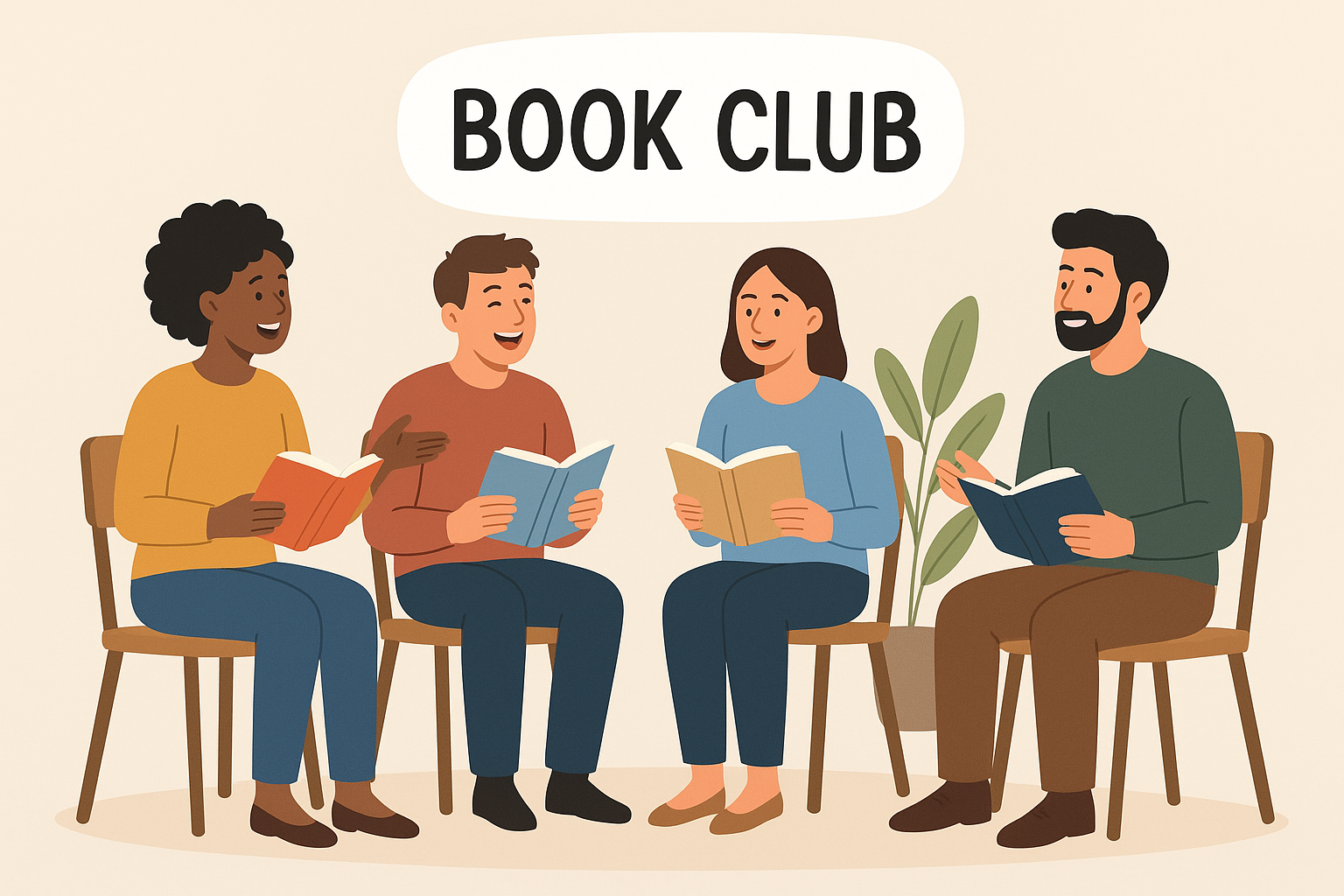事務局長の馬渡です。
◆生まれて69年、初めて読書会に参加しました
2024年3月に大学を定年退職、人生で初めて無職になった。生活環境は様変わりし、時間はたっぷりある。でも反対におしゃべり機会は激減。下手をすると日がな一日会話のない境遇に陥った。会話ゼロがよくないことは以前から聞かされていたが、実際自分がその立場になってみて、よくわかった。きつかった。だめだ、これがずっと続いたらボケてしまうよ(笑)。
ゼミの卒業生たちは時々食事に付き合ってくれる。昨年の初夏だったかに飲んだ時、会話がないとつらいよみたいな話をしたら、一人が声をかけてきてくれた。「先生、読書会に入りませんか。私が入れてもらっている読書会、楽しいですよ。ひと月に一冊程度、宿題の課題図書を読んで、みんなでおしゃべりするんです。どうですか?」。
2024年3月に大学を定年退職、人生で初めて無職になった。生活環境は様変わりし、時間はたっぷりある。でも反対におしゃべり機会は激減。下手をすると日がな一日会話のない境遇に陥った。会話ゼロがよくないことは以前から聞かされていたが、実際自分がその立場になってみて、よくわかった。きつかった。だめだ、これがずっと続いたらボケてしまうよ(笑)。
ゼミの卒業生たちは時々食事に付き合ってくれる。昨年の初夏だったかに飲んだ時、会話がないとつらいよみたいな話をしたら、一人が声をかけてきてくれた。「先生、読書会に入りませんか。私が入れてもらっている読書会、楽しいですよ。ひと月に一冊程度、宿題の課題図書を読んで、みんなでおしゃべりするんです。どうですか?」。
◆こんな読書会です
善は急げ。さっそく連れて行ってもらった。部屋に入ってすぐ、いろんな人がいることにおどろいた。声をかけてくれたゼミの卒業生は20代。だから若い人たちばかりなのかと思っていたらそうではなく、一番年上はたぶん60代のご年配。30代、40代、50代と散らばっていて、しかも男女もおおよそ半分ずつ。絶妙なバランスだ。そして皆さんの自由闊達な持論展開にまたびっくり。一冊の本をいろいろな読み方ができるんですね。いや、実に素晴らしい世代間交流の場になっていた。
2回目以降もずっとそんな調子。対話の楽しさに取り込まれ、あれよあれよという間に出席回数が増えていった。読んだ課題図書も色々だった。今、1年と2か月ほどで、課題図書は16冊読了。会に入っていなければたぶん一生手にしなかった本が多数あった。ありがたいことだ。わずかでも自分の世界が広がった。新しい仲間ともつながった。ボケ防止にもさぞや有効だったはず(笑)。
善は急げ。さっそく連れて行ってもらった。部屋に入ってすぐ、いろんな人がいることにおどろいた。声をかけてくれたゼミの卒業生は20代。だから若い人たちばかりなのかと思っていたらそうではなく、一番年上はたぶん60代のご年配。30代、40代、50代と散らばっていて、しかも男女もおおよそ半分ずつ。絶妙なバランスだ。そして皆さんの自由闊達な持論展開にまたびっくり。一冊の本をいろいろな読み方ができるんですね。いや、実に素晴らしい世代間交流の場になっていた。
2回目以降もずっとそんな調子。対話の楽しさに取り込まれ、あれよあれよという間に出席回数が増えていった。読んだ課題図書も色々だった。今、1年と2か月ほどで、課題図書は16冊読了。会に入っていなければたぶん一生手にしなかった本が多数あった。ありがたいことだ。わずかでも自分の世界が広がった。新しい仲間ともつながった。ボケ防止にもさぞや有効だったはず(笑)。
◆ソーシャル・イノベーションへの活用は如何に
ソーシャル・イノベーションに関し、日本ソーシャル・イノベーション学会は次のように述べている。「学会は、研究と実践の刺激的で充実した交流から、新しいアイデアや人と人のつながりを創発していく場にしたいと考えています」(出典:学会ホームページ)。
なるほど、つながりを創発する場か。ソーシャル・イノベーションの要諦が社会における革新的なつながりづくりと考えれば、学会自らがつながりづくり役を率先して担おうというのはよくわかる。まてよ、それなら読書会は、その第一歩=つながりの種火づくりの方法としてよいのではないかな。メリットはすぐに思い浮かぶし。
1. 属性に関わらず参加し議論できる。老若男女、職業、キャリアタイプ等の違いなく参加し、壁なく自由に議論できる。属性や所属を超えたつながりができる。つながりたい人を指名もできる。社会の中に革新的なつながりの芽を仕込みたいときに使えないか。
2. 自由にテーマを選べる。目指すソーシャル・イノベーションに合ったテーマの本を自由に選べる。
3. どのような場でもできる。空間を超えてオンラインでも、リアルなフィールドでも、場の形は意のままに。関係人口づくりなどにも使えたりするはず。
何か、いい活用法がありそうに思えてなりません。
ソーシャル・イノベーションに関し、日本ソーシャル・イノベーション学会は次のように述べている。「学会は、研究と実践の刺激的で充実した交流から、新しいアイデアや人と人のつながりを創発していく場にしたいと考えています」(出典:学会ホームページ)。
なるほど、つながりを創発する場か。ソーシャル・イノベーションの要諦が社会における革新的なつながりづくりと考えれば、学会自らがつながりづくり役を率先して担おうというのはよくわかる。まてよ、それなら読書会は、その第一歩=つながりの種火づくりの方法としてよいのではないかな。メリットはすぐに思い浮かぶし。
1. 属性に関わらず参加し議論できる。老若男女、職業、キャリアタイプ等の違いなく参加し、壁なく自由に議論できる。属性や所属を超えたつながりができる。つながりたい人を指名もできる。社会の中に革新的なつながりの芽を仕込みたいときに使えないか。
2. 自由にテーマを選べる。目指すソーシャル・イノベーションに合ったテーマの本を自由に選べる。
3. どのような場でもできる。空間を超えてオンラインでも、リアルなフィールドでも、場の形は意のままに。関係人口づくりなどにも使えたりするはず。
何か、いい活用法がありそうに思えてなりません。